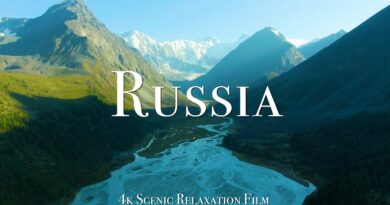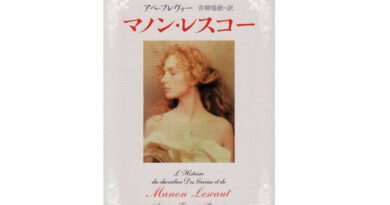「父の死」
昨年の秋に父親を見送ったある女性の手記です。
自宅で亡くなる
2020年11月18日 朝10:30過ぎ、自宅で父が亡くなった。75歳だった。11月8日に脳の血管が詰まり倒れてから10 日後のことだった。死因は胆管癌。癌の末期症状の一つに、トルソー症候群と呼ばれる血栓ができやすくなる症状があるそうで、それによって引き起こされた脳梗塞をきっかけに、飲み食いできなくなったことが、父の死因に思えた。父は、癌の痛みや苦しみを感じることはなかったために、癌になったという自覚が本人にも私にも乏しかった。癌と言うよりも、人間は、食べたり飲んだりできなくなると死ぬ、と言うように私には思えた。
父は、2019年初夏に胆管癌ステージIVbと診断され、その年の9月から抗がん剤の治療が始まった。ちょうど治験プログラムをやっていると言われ、元々、血圧や血管状態などが比較的健康だった父は、検査の結果、条件に合格し、都内の一流と言われるA病院で治験に参加することになった。治療が始まってから1年2,3カ月くらいは生きたことになる。
結果、A病院でひどい目にあうことになるのだが(少なくとも私はそう思っている)、結論としては、2020年8月7日に2回目の入院から戻った父は、在宅看護となった。父はそれまでのように大病院にかかりたかったのかもしれないが、A病院への不信感と強い怒りからとても元には戻せなかったし、また、約1ヶ月少しの入院で歩けなくなってしまった父を電車に乗せて東京のA病院まで通院させることも不可能で、私としての“当たり前”の選択をしたことが、在宅診療の認識もあまりないまま、在宅医療が始まったのだった。
訪問診療の医師や看護師は待ったなしなのですぐに体制が整うが、介護サービスは介護認定を受けるまでに時間がかかるため、ヘルパーさんが家に来てくれる状態になるまでには時間がかかった。私はちょうど1週間程度の夏季休暇を取っていたが、その間には介護の体制は整えることはできなかった。
退院した8月の時点では、医療保険と介護保険の違いも、介護保険で何ができるかも良くわかっていなかったが、平日の4日乃至5日は医師、看護師、ヘルパーさんの誰かが父の診療や介護のために家に来てくれる体制を整えていたことで、最期に自宅で看取ることができたと思う。11月に脳梗塞で倒れた時に病院に運ばれたが、入院させずに自宅に戻すと決断できたのも、その時すでに入院以外の選択肢を持っていたためだった。入院すると、コロナのために家族は殆ど会うことができない。脳梗塞で運ばれた病院では、1日に決まった時間の10分だけ面会ができる、その時に来られるのは家族2名のみ、と説明を受けた。しかし、脳梗塞が原因なのかはわからなかったが、目が覚めても二言、三言会話を交わしただけでまたすぐに眠ってしまう父とは、そのような面会スケジュールでは、とても彼が家族と会ったと思えるようにできるとは思えなかった。家族2名しか行けないのも、こちらは母と私と弟がおり、これも無理だと思った。
それで、脳梗塞で運ばれたB病院から、自宅に連れ戻すことにした。この時も、認識はしていなかったが、いわゆる終末医療というやつを自宅でするという決断をしたのだった。私は、その時には、父が確実に死に向かっているということも、何が終末医療なのかも良く認識していなかった。このままの状態であれば1週間で死ぬと言ったのは在宅医療の医者だった。そう言われても、「このままの状態であれば」という仮定の言い方には、「このままの状態でなければ」という仮定もあるように思っていた。
B病院から連れて帰る
脳梗塞で運ばれたB病院では、何が原因でこうなっているかはもっと調べないとわからない、と言われた。血管を詰まらせたと思われた血栓は運よく無くなっているようだが、MRIでは映っていない箇所に血管が狭くなっているところがあるようで、座ったり立ったりといった体を起こした状態だと血圧が下がったままになり意識不明となるのかもしれない、と言われた。脳梗塞であれば、体を起こした状態で意識がなくなるわけではないそうだ。検査をするには、検査のための薬を飲み、1日や2日程度の時間がかかると言われた。その分、入院も長引く。今起きている症状の原因を突き止め、そこから作戦を立てて、やっつける。原因の特定が必要とのことだった。
しかし、原因がわかったところで、血液が凝固しないような薬を使うことはできず、今の状態を緩和するような処方もなく、病院にいたところで快方に向かわせる明確な方法はないとのことだった。であれば、原因を探るために父の体を痛めつけるのは無益に思われた。
入院は、A病院で懲りており、家族にとってはトラウマのようになっていた。意識も記憶も明晰なので、父がふと目が覚めた時に、家族もおらず、機器に囲まれてひとり病院にいることを認識するだけという状態にするのは、感情的に無理だった。「Hさーん、目をあけてくださーい」「右手を動かしますよ!」など、何度も何度も飽きるほど多くの患者に同じ声掛けをしているとわかる看護師のやや機械的な大きな声と、その声とともにテキパキと父の体やくるんでいる毛布を動かすスピードから、父自身の適切なタイミングを無視して強制的に起こしたり、動かしたりしているように感じられ、はらはらした。
一刻も早く家に連れて帰りたかったが、目覚めた時は意識はしっかりしていても、体を起こすとしばらくして意識を失ってしまう父は、ストレッチャーに寝かせたままでしか運べないことがわかった。そのため、介護タクシーの手配が必要で、いずれにしても翌日ではないと動かせないということになった。
長い長い一日だった。11月10日午後3時頃に、椅子に座ってテレビを見ていた父が、突然、ぐにゃりと体が曲がり、意識がなくなったそうで、それを見た母が救急車を呼んだ。
病院から母が私に電話をかけてきた。看護師さんからも電話があった。都内の自宅からさいたまの病院に私が着いたのが午後5時頃。その後すぐに弟とも病院で合流した。病院の待合室は、コロナ感染を予防するために、あちこちのドアを開けており、寒かった。
家族3人で待合室で待つ、医師から今何をしているかの説明を受ける、また待つ、医師から診察結果の説明を受ける、それが夜9時頃だったか。脳梗塞が起こったが、詰まった血栓は運よくなくなったようだと説明を受けて帰宅できることになったが、トイレに行ったところで父が倒れた。そこからまた検査をすることになり、説明を受ける、待つ、ストレッチャーに寝かされている父を見に行く、待つ、医師から説明を受ける、待つ、入院の説明を受ける、待つ、病室に入って寝ている父の顔を見に行く、待つが繰り返され、ようやく会計を終え、帰宅したのが朝5時頃だった。
入院の説明を受けたのは、夜中の3時頃だったと思う。この時に面会時間のことも説明を受けた。シフト制とは言え、普段、このような仕事の仕方をしている人がいるのかと思うと、頭が下がった。家族にとっては病院は、一つ一つの出来事の間の待ち時間が異様に長く、進路や出口がわからない迷路のようだった。
朝5時過ぎに帰ってきて、私はその日は仕事をしたのだろうか。私が勤めていた会社は、オペレーションが最悪で、入社したばかりの人が「野戦病院のようだ」と形容するような、常に非常事態の切羽詰まった状態だったから、突然完全に休むことに気がひけて、少しは仕事をしたかもしれない。
ひと眠りした後に、訪問看護士と訪問医師に電話を掛け、病院で受けた説明を伝える。どうすれば良いかわからないことも伝え、しかし、病院に置いておいても快方に向かう治療ができないのであれば、家に連れて帰っても同じことではないか、と伝える。在宅診療の看護婦からは「うちとしてはどういう状態であってもちゃんと看る」と言われ、訪問看護師及び医師と、自宅に連れて帰ることの確認をとった。
医師も看護師も、自宅で終末医療をする、自宅で父を看取ることをわかった上での話だったと思うが、この時の私にはわかっていなかった。父は、目が覚めている時は、記憶も意識も明晰、自分でも大したことないと思っているようで、「自分で歩ける」「全然大丈夫」「何が食べたい」「あれが食べたい」「H(弟)もいるからみんなで鍋をしよう」と元気があった。それにこの時は、目が覚めている時間も長かった。すぐに寝てしまうということもなく、目が覚めれば、寝たきりのようになる状態が不満でテーブルの席につきたがり、話もしていた記憶がある。実際、家族が止めるのも聞かずに、電動ベッドから自分で起き上がって床に降りて歩いた。しかし、テーブルまで行き、椅子に座った後しばらくして、動けなくなった。また、ベッドからトイレまで歩いていき、トイレに座った後に、動けなくなった。動けなくなると、慣れない家族が3人がかりで持ち上げたり動かしたりしないと、動かせなかった。
家族も本人もしばらくすれば、また動けるようになるのではないかと思ったが、そうはならなかった。8月に退院した時には、立ち上がれなかったのが立ち上がれるようになり、歩けるようになり、おかしかった頭も治っていった。一度、回復した状態を見ていたので、少しは良くなる、もしくは、介助に慣れない家族も何かコツをつかめば、父の可動域が広くなるなど、今よりましな状態になるのではないかと思っていた。
しかし日を追っても、良くはならなかった。目が覚めて、おなかが減ったと言うが、食べ物を口の中に入れても噛んでいるうちに寝てしまう。頭ははっきりしていて、目が覚めると「ソフトバンクは勝ったか(日本シリーズの頃だった)」「トランプは敗北宣言をしたか」と聞いてくる。相撲の結果を新聞を見て読み上げると、気になっている力士の結果にはかすかに頷く様子が見られる。起きている時にテレビの相撲中継の音を耳にして結果を覚えているのか、中日の勝ち負けもわかっている様子だった。
おなかが減って減って、食べたくて食べたくて仕方がないが、食べられない。このまま水分も栄養も取れずに寝たままであれば、弱って死んでしまうのは、素人でもわかる。病気の時に快復するのは、水分を取って食べるからだ。それができない年寄りは、筋力もますますなくなり、どんどん弱っていってしまうだろう。退院した時に、在宅診療の医師からは、点滴は脳内の血管を膨張させてしまうことがあり、そうなると意識がなくなる、何が起こるかわからないのでやらない方がいい、と言われていた。しかし、食べたがるのに、水分を取ることも食べることもできない状態が続いている。父を飢え死にさせているようだった。
退院後、週1回だった訪問看護は、毎日行ってもらっていた。時には、家族の呼び出しに応じ、日に2度、3度と来てくれた。日々、刻々と状態が変わるので、その度に悩みが出る。せめて水分や栄養を少しでも取れるように、点滴を打つ方が良いのではないか。点滴の件は、何度か話をしていたが、ある時、診療に来てくれた医師を引き留め1時間くらい話をし、夜来てくれた看護師さんを狭い部屋に押し込め夜10時過ぎまで2時間以上話をした。目が覚めた時にまず水分や食べ物を欲しがるが嚥下できない父に、点滴を行わないというのは、私は正しい判断をしているのか。これで良かったのか、少しは快方に向かうチャンスを壊しているのではないか。
看護師さんは、今や3名体制で、24時間看護を支えてくれていた。我が家には来ない看護師さんもこの体制を支えてくれていたのかもしれず、もっと沢山の方々に助けてもらっていたのかもしれない。
ベテランの看護師さんが、父に、咀嚼や嚥下の仕方を指導し、脚や手のリハビリをしてくれた。左の方が動かなくなってしまった父は、右の歯で咀嚼をし、右の方に持ってきて飲み込むようにと指導している。「口のまわりの筋肉をマッサージして、こうするともっと噛む力もついてくる」と話しながら、父の口周りを触っている。ベッドに寝てはいるが、脚や手を介助を得ながら動かし、蹴ったり握ったりする。「すごいすごい。さっきより動けるようになっている。こうすれば、もっと蹴れるようになる。」といつものように明るい声。
彼女が帰る時に玄関先まで送っていき、会話をすることがたまにあった。この日もそうだった。
「人間は、死に向かっている時でもどんな時でも、何かに向かって進んでいるというのが大事なの。」
父は間もなく死んでいくけれども、脚の筋力がついて良く蹴れるようになるために脚の運動をしたり、口の周りのマッサージをして噛む練習をすることで嚥下ができるかもしれない、と言うのが大事で必要なことなのだった。
「未来に向かっている、前進している、というのが、どんな時でも大事なの。」
リハビリの様子を覗き見た私は、父が快方に向かう錯覚をしていた。父は嚥下の練習を看護師さんに言われた通りにまじめにし、脚の力も強かった。治ったら嚥下したり、蹴る力をつけておくことは歩く時の助けになるのかもしれない。もしくは、今の状態を長く維持できるのかもしれない。私は、リハビリの様子を本気で応援して、彼の数分間の努力やその進歩に彼の前で素直に喜んだ。
でも、彼女との会話の最中に、退院させた時には理解していなかった自分の決断の意味に、突然気づいた。「私たちは、いわゆる終末医療というのを、家でしているということなんですね。」と問うと「そうだ」と肯定された。
「親が死んでいくのを見ることは子供にとっても良い経験になる。これからお父さんは、今までできていたことを一つずつ手放していくことになる。そうやって死に向かう準備をしていくの。」
「男の人の方が、あれもできない、これもできないとなったら、もういいや、ってあっさりとあの世に行っちゃうことが多いのよ。女の人の方が、できなくなった状態に順応して、いつまでも生きていたりするのよ。」
死ぬ時には、その人らしさが表れる。
「お父さんは弱っていくばかりじゃなくて、人間は意外に強いところがあるのも見ると思う。死に向かっていくのは大変だから、一人じゃないよと家族は見守って応援して、一緒にいてあげればいい。
お別れは少しの間で、またあの世に行ったら会えるから。」
「私や弟は、父が死んでくということがわかっているんですが、母はわかっていないようなんですよね。」
「お母さんはお父さんと一緒に子供を育て上げたという成功体験があるからね。いろいろあったけど、最後には一緒にやった成功体験になっているから、子供のように離れては見られない。家族で一緒にいるのはどれくらいぶり?久しぶりに元の家族だけで一緒にいるのも良い経験ね。在宅看護をしたくでもできない人もいっぱいいるし。親から遠くに住んでいたらできないし。」
最期の8日間
最期の8日間は、弟も殆ど実家に泊まり込み、実家から通勤していた。私の場合は、コロナのおかげでフルリモートワークが可能になっていた。A病院で父がおかしくなったのはコロナのために面会ができなかったせいもあったかもしれないが、在宅で看病できたのもコロナのおかげとも言える。
私は食事係でもあった。退院した日に、少しでもおいしい流動食をと思い、出汁をとって作ったコーンポタージュや、土鍋で炊いた重湯は、父の口に入らないまま終わった。薬局で買った吸い口は、8日間の最初の2日くらいは使えた。そのうち、起きて何かを口に入れてもすぐ寝てしまうようになった。誤嚥が危険なので、飲み物や食べ物をあげられなくなった。みかんを手で絞ったものや、お茶をガーゼに浸して、起きた一瞬を勝負にそのガーゼを口に入れて、少しだけ味わってもらう。
おむつを替えるのは、看護師さんがやってくれていたが、それだけでは足りないので、母と二人でも良く行った。ある夜、父が寝る前に、仕事から帰ってきた弟と二人で行えたことがあった。弟と「これをとって」「そっちをもって」と子供の頃のようにお互いに声を出して協力してできた。嬉しかった。親不孝だったので、悔いが残るのを少しでも軽くしてくれるように、父が機会をくれたのだろうと思った。感謝している。
そのうち、痰がたまるようになり、吸引機の使い方を覚えた。
最初の頃は発話して話ができていたのが、だんだん、かすれ声で何を言っているのかわからなくなった。でも、右手や右脚は元気で、力もある。こちらの言っていることが正しい時は、右手の指でマルを書いたり、ジェスチャーをする。右手にマジックを握ってもらい、寝たまま、こちらが持った紙に文字を書いて、言いたいことを伝えてもらうようになった。
亡くなる前日の朝6時頃、父の言葉を何とか理解し、父の依頼通りに叔父に電話を掛けた。電話ではかすれた息で余計に何を言いたいかわからないから、伝えたいことを書いてもらった。叔父(父の弟)は、Go Toを使って旅行に行こうと父を誘ってくれていた。「せっかく旅行に行こうとしていたのに、こちらが倒れて行けなくなってしまった。こんなことになってしまってすまない。」という内容だった。
息も苦しそうで、発話を理解するのは難しくなっていたが、頭は相変わらずはっきりしている。その日の夜には、父の母方の実家で飼っていた犬の話を私がして、その犬の頭数を聞き、指で答えてもらっている。
亡くなる日の朝6時過ぎ、父の酸素濃度が下がり、看護師さんが駆けつけてくれた。いったん帰った後、9時頃に、看護師さんとヘルパーさんが二人で来て、体を拭いて着替えさせてくれた。はあはあと息は苦しそうになっている。ヘルパーさんが、「Hさぁん、T橋ですよぉー。おはようございます。わかったら、右手で握ってくれますか」と手を握りながら挨拶をしたら、ふわっと握ってくれたそうだ。
看護師さんとヘルパーさんが帰った後、30分もしないうちに亡くなった。
私は、親不孝な娘だった。親とは疎遠で、反発をしていた時期も長い。思春期の子供のような態度をとっていた時期も長かった。連絡をせず、会わず、拒否もした。正直、父親のことは嫌いだったと思う。イヤだった。尊敬はしていなかった。バカにしていたのかもしれない。私は、自慢できるような仕事もしておらず、結婚もせず、子供もいない。孫もいないので、会う理由も余計にないように思っていた。彼が元気な時に、ただ、ごはんを一緒に食べるとか、普通のことをもっとたくさんしておけば良かった。一緒に旅行に行くとか、どこかに食事に行くとか、特別なことじゃなくて良かったのだ。
もう一つの後悔は、家族を優先しなかったことだ。9月の三連休明けに東京の自宅に戻り、11月に父が倒れるまで実家に行かなかった。当時の上司に、父の具合を尋ねられ、「いつまで実家にいるのか、このままいつまでもいるわけにもいかないわよね」と言われたことが、自宅に戻るきっかけになった。私の人生においてどうでもいい人の言葉になぜこんなに影響を受けてしまったのか。また、11月の看病の時も、もっと思い切って仕事を休めば良かった。父が亡くなる朝に、父のベッドのそばに付き添っていた母と弟を横目で見ながら、仕事のパソコンを開いてパチパチやっていた。良く考えれば、そこまで緊急なことはなく、退職した今となっては、あんなのはどうでもよかったことだと思う。あの時の仕事や職場環境に、洗脳されていたような気がするのだ。