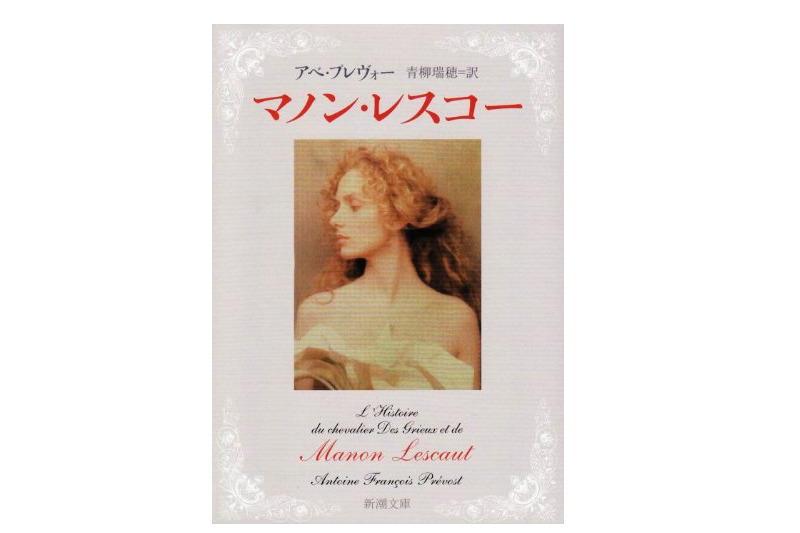
「マノン・レスコー」はフランス文学の伝統らしい小説ということで読んでみた
恋愛小説はフランス文学の伝統で、「ファム・ファタル」はまさにフランス恋愛文学ならではとのこと。「ファム・ファタル」は、ユニークな概念だからこそ的確な訳語もなくそのまま使われているのだろう。今から約300年前に書かれたファム・ファタルの代名詞「マノン・レスコー」は、「フランス文学の伝統らしい小説」ということで読んでみた。
1.あらすじ
『マノン・レスコー』は主人公の青年が熱烈な恋に落ちた女性の名前で、原題は『xxxと騎士グリュウの物語』。作者はアントワーヌ・フランソワ・プレヴォー、1731年発表。300年近く読み継がれ、今読んでも十分面白い。学業優秀、品行方正で教師や学友からも一目置かれていた貴族の若き青年グリュウが、町で偶然目にした美少女マノン・レスコーに一目惚れして駆け落ちし、彼女のためにお金を稼ぐべく賭博、詐欺、あげくの果てには殺人と、数々の犯罪を重ねて身を持ち崩していく。最後、グリュウが犯した詐欺に巻き込まれたとも言えるマノンは、当時、流刑地でもあったアメリカに送られることになる。グリュウは貴族という特権階級ゆえに釈放されたものの、自らマノンについてアメリカに渡る。アメリカでマノンは死に、グリュウは、遠方はるばる自分を探しにアメリカまで来た友人チベルジュとともにフランスに帰国する。物語は、マノンを亡くしてフランスに帰国したばかりのグリュウが、作者にマノンと自分の物語を語るという内容になっている。
2.マノンは謎に満ちた魔性の女?
マノンは、「ファム・ファタル」の代表と言われてきた。謎に満ちた運命の魔性の女、天性の娼婦気質、純情な男を破滅させる悪女、、、と言うように。しかし、#Me tooやジェンダーギャップなんかが話題に上る現代の我々から見た時に、果たして、マノンってそんな風に言われる女なの?という印象が強い。(余談だが、謎に満ちた魔性の女、なんて言われると、個人的には、例えば、水城せとなの「失恋ショコラティエ」のサエコさんなんかの方がよっぽどそれに近い。)
恋愛って非対称。自分視点だと惚れ込んだ相手が何を考えているかわからない。
まず、マノンに熱烈に恋しているグリュウの視点で、徹底して一人称で書かれているために、「マノンってどういう女なのかわからない(何を考えている女なのかわからない)」となるのだと思う。特に読者がグリュウに共感(しようと)しながら、グリュウ視点でマノンを見てしまうとそのように感じるのではないかと思われる。
なぜって、多くの恋愛は非対称なものなので。特に、自分が相手に惚れ込んでいるのに、相手はそこまで自分のことが好きではない時や、自分の思いの方が相手よりもかなり大きい時は、相手が何を考えているかはなかなかわからない。自分のこと好きなんだ、と思ったら、裏切られたり。でも、それは、自分に対する相手の思いを推し間違っていただけだったり。現実世界では、小説やドラマのような神の視点はないので、自分が片思いしているような相手は何を考えているのか、ほれ込んじゃっている方はよくわからない。
この小説の面白さは、現実世界のように徹底して一人称で、自分の細かな心情や相手の様子を、ある意味、ものすごく誠実に描き切っているところにあると思う。「私が好きな相手が私ほど私のことを好きではない」時、もしくは、「私と同じ形で私を愛してくれない」非対称の恋愛の普遍性がある。グリュウのことはみっともないと読む人も多いかもしれないが。
若くてモテる美貌の女は分別がついていない
マノンは大変美しくてモテる若い女なのも、「浮気性の女」「男を破滅させる魔性の女」と言われてしまう原因だと思う。分別のつかない若いうちは、言い寄られるのが当たり前過ぎて、人を好きになる純粋さや真剣さがわからない可能性がある。自分が誰かを好きになる経験をする前に、好きでも嫌いでもない男がひっきりなしに寄ってきて、自分が他の男と関係を持ったとしても許されるような関係で男女関係を学んでいれば(年配の男性が地位や財産で彼女を釣っている時や、男性が彼女のことをとにかく好きな時)、恋愛に真剣な思いがあるなんて気づかないかもしれない。
たとえその関係がダメになっても次があるし、向こうから言い寄られた関係だし、一つ一つの関係はあまり貴くない。これが、容色が衰えるとかで、言い寄ってくれる男性がいなくなれば、一つ一つの関係が貴重になってくる。
もしくは、自分が本当に好きな男性ができて、その思いがかなわない経験でもすれば、人を好きになる痛みがわかるようになる。それで、相手への想像力が働くようになって好意を寄せてくれた人には誠実で優しい態度も取るようになる。(かもしれない。)でも、マノンはまだ16歳。そしてとにかくモテてモテて仕方のない美少女なのだ。マノンがどう思っていたかの描写は一切ないので(前述のようにこの小説の素敵なところ)、マノンがどうだったのか、想像してみる。
マノンにしてみれば、資産もなく、特権階級に生まれたわけでもないが、持って生まれた美貌のせいか、ちやほやされて、有り余る財産が提供され、それなりに豪華で愉快な生活をさせてくれるのは、楽しいことだったのだと思う。こういう生活をしたい場合、この時代には職業婦人とかキャリアウーマンみたいな存在はないので、マノンのような方法くらいしか、なかったかもしれない。マノンは美しく生まれて、非常にモテたので、ラッキーだったかもしれない。
後先考えない若者の特権も手伝って、楽しいこと優先の刹那的な態度になるのも仕方ない。
マノンにとっては、一目惚れで熱烈に自分に好意を寄せるグリュウは、当初は「別にどっちでもいい」みたいな存在の、突然降ってわいたような存在だったと思う。自分から好きになったわけではない。グリュウが言い寄ってきた時には、彼女には、ビッグなパトロン(恋人)― ただしかなり年配 ―がいたし。
若くてイケメンで良いとこの出の、自分にぞっこんなグリュウのことは好きになったけれど、グリュウと同じほどには好きではない。グリュウとの恋愛は楽しかったと思う。熱烈に自分に恋しているグリュウに誠実に接するには、長期的で広い視野が求められる分別が、彼女にはまだ足りない。若さのせいなのか、教育のせいなのかはわからない。
若い彼女にとって、一番心惹かれる男性は、同じように若くて経済力がある男性なのではと思う。資産家の男性と愛人関係になることで経済力を得ているが、自分の父親かそれより年上の男性よりも、同じ条件ならば、若くて見目麗しい男性の方が良いだろう。自分も若くて美人なんだから。彼女は、より高い地位を得たいとか、より金持になってもっと贅沢をしたい、と言うような上昇志向はない。パリと郊外の別荘を行き来しながら、芝居見物をするような楽しい生活は必要だが、際限なく贅沢を求めるタイプではない。なので、時に、今の恋人よりも経済力も地位もあるが、年上で醜い男性から言い寄られても、なびくわけではない。だけど、今の恋人より経済力も地位もある若い男性がちやほやしてくれるなら、話はまた別。
経済力、若さ、見た目のバランスは大事だが、言い寄ってくる男性になびいてしまうのは、自己評価はそんなに高くない女性なのかもしれない。したたかというよりは、まだあまり分別のついていない若い女の子、というような印象を受ける。
そんな彼女が、禁欲的な生活をしてまでグリュウに一途になるには、パリは「雑音」が多すぎる。言い寄ってくるお金持ちの男性は次々現れるし、オペラ座の芝居は好きだし、素敵な洋服も必要だし買いたいし、社交界もあるし、別れたはずの元カレと出会ったりするし、とにかく人もモノもエンタメも多くて、グリュウと「二人だけの関係」に集中するには誘惑が多い。
だから、そういった「雑音」のなかったアメリカでは、初めてグリュウが望むような関係になることができた。最後、グリュウの目に、彼女が本当の愛に目覚めたように見えるのは、そもそも楽しい芝居や素敵な洋服や住居などお金を使う先もないので、財産を持っている男がそこまで彼女にとって重要じゃなくなったことや、見ず知らずの地で頼れる人がいなかったこともあったと思う。グリュウのことは、元々、(それなりに)ちゃんと好きだったわけなので。
アメリカは二人の関係を壊すような誘惑がなかっただけではなく、アメリカに渡る前に、アメリカについてくるのは止めてほしいとグリュウのためを思ってマノンは泣いて懇願したのに、グリュウは譲らなかった。そこまで愛されればさすがに深い情も沸くのもあったと思う。
3.元祖 ロマンチック・ラブ・イデオロギー(恋愛至上主義)?
この小説、最後の方で、恋愛至上主義の「ザ・ロマンチック」を解き放ってくれる。マノンが死ぬところでもアメリカでの生活でもなく、グリュウがアメリカに渡る前に語るところで、恋愛至上主義万歳、というような瞬間がやってきた。ロマンスには、多分に自分に酔うことが必要だ。グリュウは、本当は自分に酔っていたのかもしれない。が、恋愛至上主義って、映画でも小説でも「純愛」とか言って、人々を陶酔させて涙させたりしている。自分に酔う「陶酔感」はある種のカタルシスをよぶ。
この小説の中盤過ぎまで、マノンにほれ込み彼女のこと以外はどうでもよくなるグリュウに対して、「どうしようもねえなぁ・・・」と思って読んでいた。学力優秀で品行方正な青年だったのに、社会的地位も義務も、親友も、司教も、父親もすべてないがしろにし、嘘をつき、詐欺を働き、賭博でいかさまを働き、捕まり、脱獄もし、ついには殺人も犯す。いくらその女が大事でも、さすがに人を殺しちゃいかんだろ。(でも元来の美貌や魅力で許される。もちろん、当時の特権階級だったからも大きいが。)何度も裏切られる友人、チベルジュも哀れである。まあ、こんなにひどい目に何度あっても、彼の友人をやめないチベルジュ君も、大丈夫か、というのもあるけれど。
彼女との二人の生活を手に入れたグリュウは、快楽的で贅沢な生活が好きで浮気症のマノンに我慢をさせたり、矯正しようとしない。お金がなくなり我慢をさせるとマノンが金持ち男と浮気してしまうことを理解しており、自分がみすぼらしい格好をし、馬車ではなく徒歩で移動するなど節約をして、マノンが馬車で郊外の家からパリに芝居見物に行ける生活をさせている。グリュウは自分の献身に対して愚痴もぼやきも一切なし。九州女が九州男児を立てるように、マノンに好きなようにさせているようで、実はグリュウがマノンの手綱を握っているようにも見える。「浮気するな」とか「贅沢しないで」と、相手に変わることは求めない。マノンはそのままでいいと肯定して、自分を変えて満足している。これって、女の子が望む関係でもある。
そうして最後、未開の地アメリカに追放処分となるマノンに、無一文になっても自ら一緒に彼女と歩いて港まで行き、船に乗ってついて行くグリュウの描写を読んで、「ここまで愛されるなんて幸せ」と思う瞬間がやってきた。普通は、アメリカ行きとなった時点でフランスに残り、この恋は終わりだろ、と損得や現実をわきまえる。「ここまでするなら、グリュウ、本物」と思ってしまった。
マノンはグリュウにとってもう信仰の対象のよう。宗教だ。元々、グリュウは神学生になることを薦められるほどに宗教的資質もある男の子だった。何かのために自分を捧げる、というのは彼の性質かもしれない。彼が犯した犯罪も裏切りも詐欺も、もうどうでも良くなってきて、この信仰に殉ずる純粋さにホロリと来た。
グリュウは述べる。
「愛しあう恋人同士にとっては、宇宙全体が祖国ではないだろうか?」
フランスだろうが、未開の地だろうが、愛し合う二人が住む場所はどこだってかまわないのだ。恋愛は世界平和も実現させるのだ。恋愛至上主義のロマンチシズム極まれり。ここまで来たら、もう貫いてほしいと思う。
見も知らぬ国でどん底に不幸せになるよりはここで一緒に死ぬか、私を殺して他の女の人と幸せになって、と言うマノンに、グリュウは、
「きみと一緒にいて不幸せなのは、ぼくにとっては願ったりかなったりの運命なんだ」
つとめて平静な態度をとって、彼女から死だの絶望だのという不吉な考えを一掃しようとした。・・・女に勇気を吹きこむには、女を愛している男の勇気をおいてほかにないことをあとになって経験したのだった。
その通り。こんなふうに女を愛してくれる男の人なら、女は安心して任せられる。最初の頃に、馬車の中で人目もはばからずマノンと乳繰り合って顰蹙を買っていたグリュウも、だいぶ成長した。
4.ファム・ファタルではなく、ファム・オム?
現在の感覚からは、やや不思議な存在に見えるチベルジュ君。彼は、グリュウの親友だが、親友以上の想いを持っていたのではないか。彼は、神の道に進む経験なキリスト教徒でもある。何度裏切られても決してグリュウへの信頼を失わず、変わらず支援し続ける。せびられれば何度でもすぐに金を渡す。地の果てのアメリカまで難破しても辿り着き、グリュウを探しにやってくる。
チベルジュが、例えば、家柄か知性がグリュウと釣り合う女性でも成立する物語だ。もしくは、チベルジュを男性のままに少女漫画化したら、チベルジュはグリュウに恋しているゲイとして設定する方がしっくり来る(売れそうだ)。
思えば、グリュウは、殺人を犯した後でさえ「どことなく高貴で品があり」、イケメンで、見知らぬ人(この小説の作者)も思わず彼に金銭をあげてしまうような、人たらしだった。グリュウ自身、自分の魅力をわかって、利用していた節もある。(それで、監獄から出してもらえた。)父親も兄も、司祭も巡査も彼には甘い。
5.青春小説?
結局、グリュウは、マノンが亡くなった後、アメリカまで探しに来たチベルジュ君とともにフランスに帰国している。そこで、再度、作者である「私」と会い、自分の物語をマノンとの出会いから語る。これから故郷へ帰るが、そこには兄が迎えに来ている。故郷に戻った後は、グリュウにとって「普通の」「元通りの」生活に戻るんだろうな、と思わせる。犯罪を犯したし、流刑地であるアメリカにも自分で望んで愛する女と一緒に行ったけど、家族は彼を許しているようだ。変わらずに元の何不自由のない生活に戻るのだろうな、と思わせる。
あれだけ入れ込んだ女は死んだが、彼の生活は変わらずに続く。廃人になるわけでもなく、アメリカに残るわけでもなく、彼にはちゃんと戻るところがあったのだ。
アメリカ追放の契機となる事件を起こす前に、自分と同じような年代の資産家である貴族階級のT氏が、グリュウに協力的で、この関係には若さゆえの純粋さを感じた。そんな「考えなし」で大丈夫か、と思う一方で、己の社会的地位や利害関係、損得なしで突っ走る愉快さがある。友の協力も得て、やんちゃして少し成長して、元の平穏無事な生活に戻った、みたいなグリュウの青春小説にも見える。
青春小説は、冒険や困難を引きづって彼の生活や人生が決定的に元に戻らないというのではダメで、彼は無事に帰還しなければならない。また、子ども時代(青春時代)の冒険や困難は、もう二度と触れることができないように、永遠に失われてしまわなければならない。
マノンは死んでしまったので、永遠になった。別々の人生を歩んだ二人がどこかで会う可能性はゼロだし、グリュウの帰還は完璧なものとなる(再び冒険や困難が始まることはない)。




